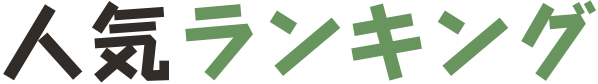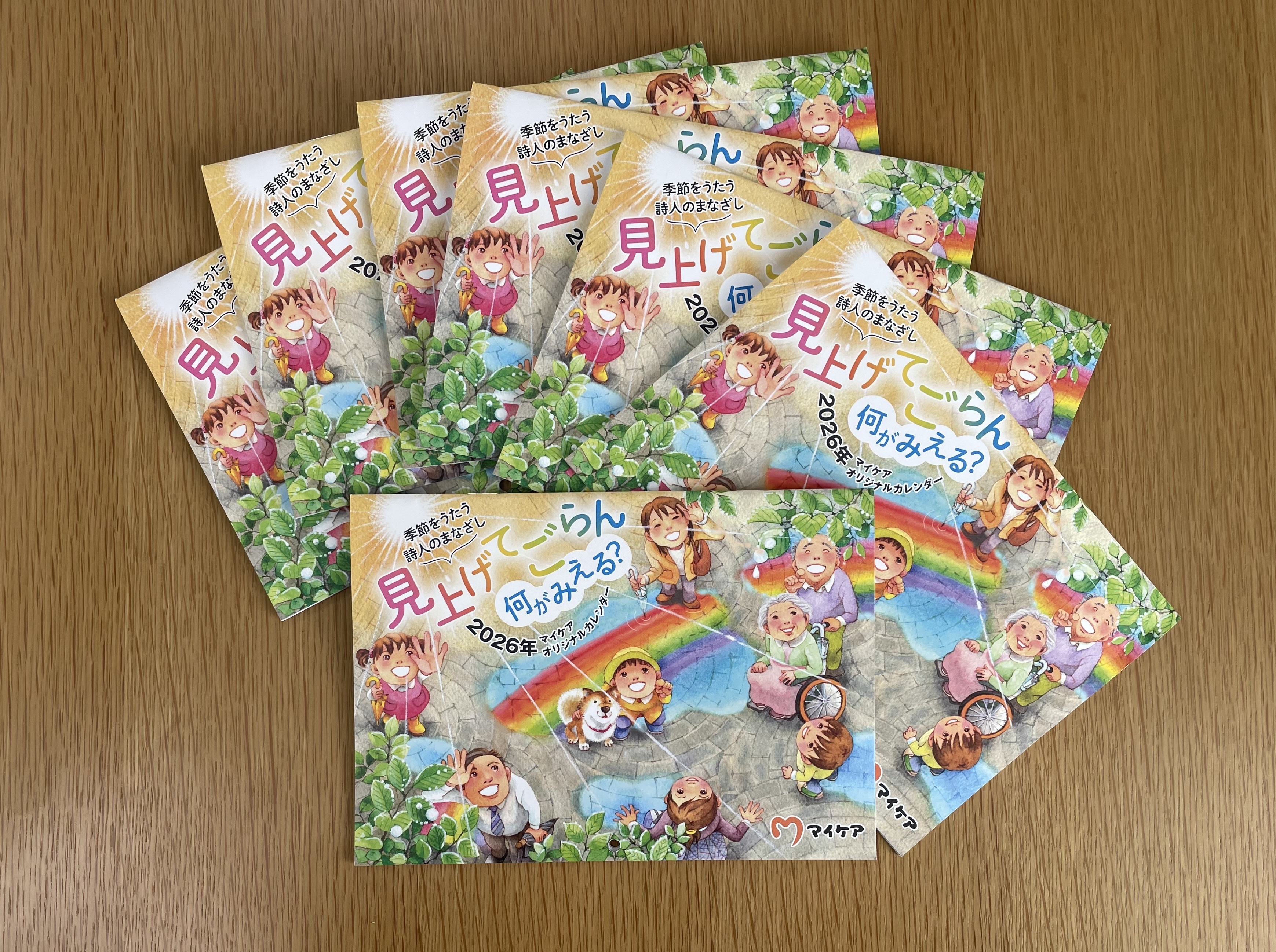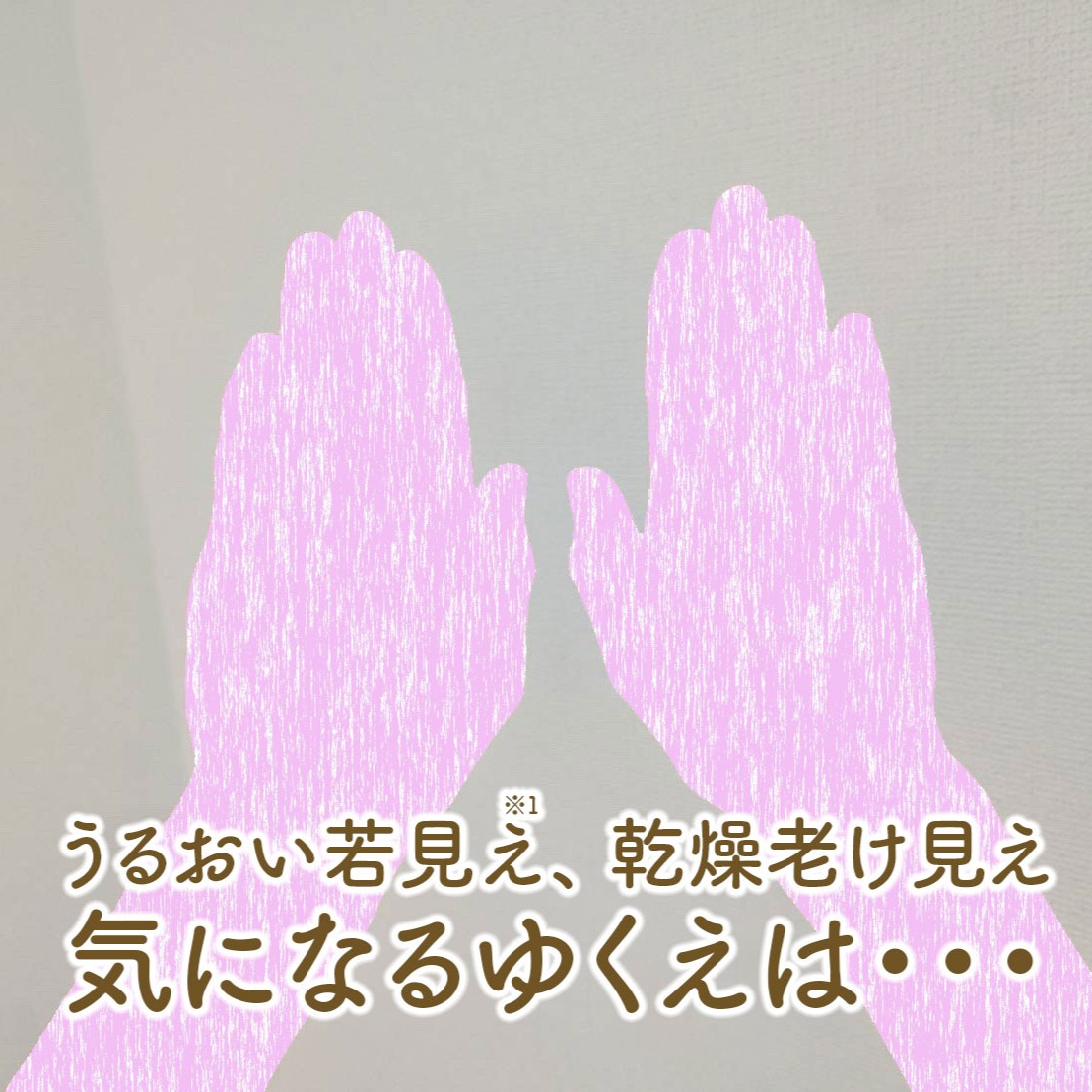2019.02.12
ふるさとレシピ 第5回『ぶり大根』

ふるさとの味を求めて全国の食卓にお邪魔する「ふるさとレシピ」。今回は富山県氷見市・室田さんちのぶり大根をいただきました。
氷見のひとをつなぐ嫁鰤(よめぶり)
氷見では荒天が喜ばれる――。
真冬の雷鳴は「ぶりおこし」と呼ばれ、鰤(ぶり)がたくさん獲れる縁起の良い天候と信じられているからなのだそうです。
室田さんのお宅を訪ねたのは丁度そんな雷雨のあがったお昼前。家庭農園から収穫した大根を手に、笑子(えみこ)さんとご主人の仁一(じんいち)さんが迎えてくれました。
「新鮮でみずみずしい大根で作るぶり大根、こんな贅沢はないわよね」
嬉しそうな笑子さんに仁一さんも、ちょっと得意そう。
「室田家の味は酒と砂糖を気前よく、それから味噌を入れるのが大切よ」
そう言って、調味料を見せてくれた笑子さんに「あんたの味付けは甘すぎるわよ~」と横から顔をのぞかせるのはご友人である久保範子(くぼのりこ)さん。
氷見生まれである範子さんはぶり大根には特別な思い出もあるそうです。
「嫁鰤といって、お歳暮になると、結婚した女性の実家から、嫁ぎ先に鰤を一尾贈るんです。切り分けた身は近所に配り、残った骨やあらを使って作るのが、ぶり大根。私が結婚した時も義母と一緒に作りましたよ」
嫁鰤は出世魚である鰤を贈ることで、嫁ぎ先のご主人が活躍できるようにという親心なのだそうです。

氷見に移り住んで以来の友人という範子さん(写真左)と笑子さん(写真右)。気の合うふたりは、支度から食事まで終始笑顔とおしゃべりがつきません。
ぶり大根も夫婦喧嘩も一晩寝かす
そんな嫁鰤の力添えもあり(?)、仁一さんは責任のある仕事を任されることが多く、20年以上も各地に単身赴任をされていたそうです。
「外食で、舌が肥えちゃって。食事にはうるさいのよ。ケンカなんてしょっちゅうね(笑)」と、笑子さん。仲直りのコツを伺うと「放っておく!」とすっぱりいって続けます。
「ぶり大根を作るのと一緒。一度冷ました方が味も落ち着くんです。さぁ、召し上がれ」。台所から持ってきてくださったのは何と笑子さん特製、「昨日の」ぶり大根です。
器によそったやわらかな大根を箸で割れば、芯までしっかり蜜の色。
つゆがこぼれないよう、大きな口で迎えると、あれ、ぶりの味がする! 香りやうまみがよく移った大根は、まるで脂の乗った寒ぶりのよう。
仁一さんも「うまいなぁ」と一言ぽつり。満足そうな笑子さんの眼差しが一層やわらかくなり、そっと小声で教えてくれました。
「本当はねぇ、私が甘口になったのもお父さんの好みなんですよ。健康のためにはもう少し薄味に慣れてほしいんだけどね」
一晩寝かせた室田夫婦のぶり大根は、甘く、深みのあるうまみがしっかりしみていました。

「お酒と調味料は気前よく!」が室田さん流。基本の調味料に加えてみそを入れると味が良く、深みが出るのだそう。
作ろう♪『ぶり大根』
冬の定番ぶり大根。作りたても美味しいですが、一晩寝かせると鰤のうまみがしみた絶品の飴色大根に。
食べる直前に温め直すと温かく、やわらかな冬のごちそうに変身します。レシピの分量は濃い口ですが、しっかり味をしみ込ませるなら薄味に仕上げても◎。
[材料] 5人分
ぶりのあら 800g
大根 1.5本~2本
水 1ℓ
酒 500ml
砂糖 大さじ2~3杯
たかのつめ 2~5個
しょうゆ 100ml
みりん 100ml
みそ 大さじ1~2杯
ゆず 適量
しょうが 適量
[作り方]
①大根は輪切りにし、皮を剥き、面取り(切り口の角を丸く仕上げる)をしたら、鍋に湯を沸かして下茹でをする。
②別の鍋に湯を沸かし、酒(分量外)を加え、沸騰したらぶりのあらを入れる。色が変わる程度に湯通ししたら、ざるにあげ、用意した氷水でぶりのあらを冷やして洗い、水けを切る。
③鍋に分量の水、酒、しょうが、たかのつめを入れ、①を加えて煮込む。大根に火が通ってから、②を加え、味を見ながら残りの調味料を加えてひと煮立ちさせる。
④一度火を止め、2時間~一晩おき、よく冷まして味を落ち着かせる。
(ケンカした場合も然り。)
⑤温める程度に火を入れ、刻んだゆず、たかのつめ(分量外)を飾る。
<2018年 新春号 Vol.39 55-58ページ掲載>














 だんらんWEB TOPに戻る
だんらんWEB TOPに戻る