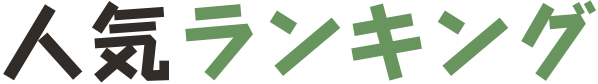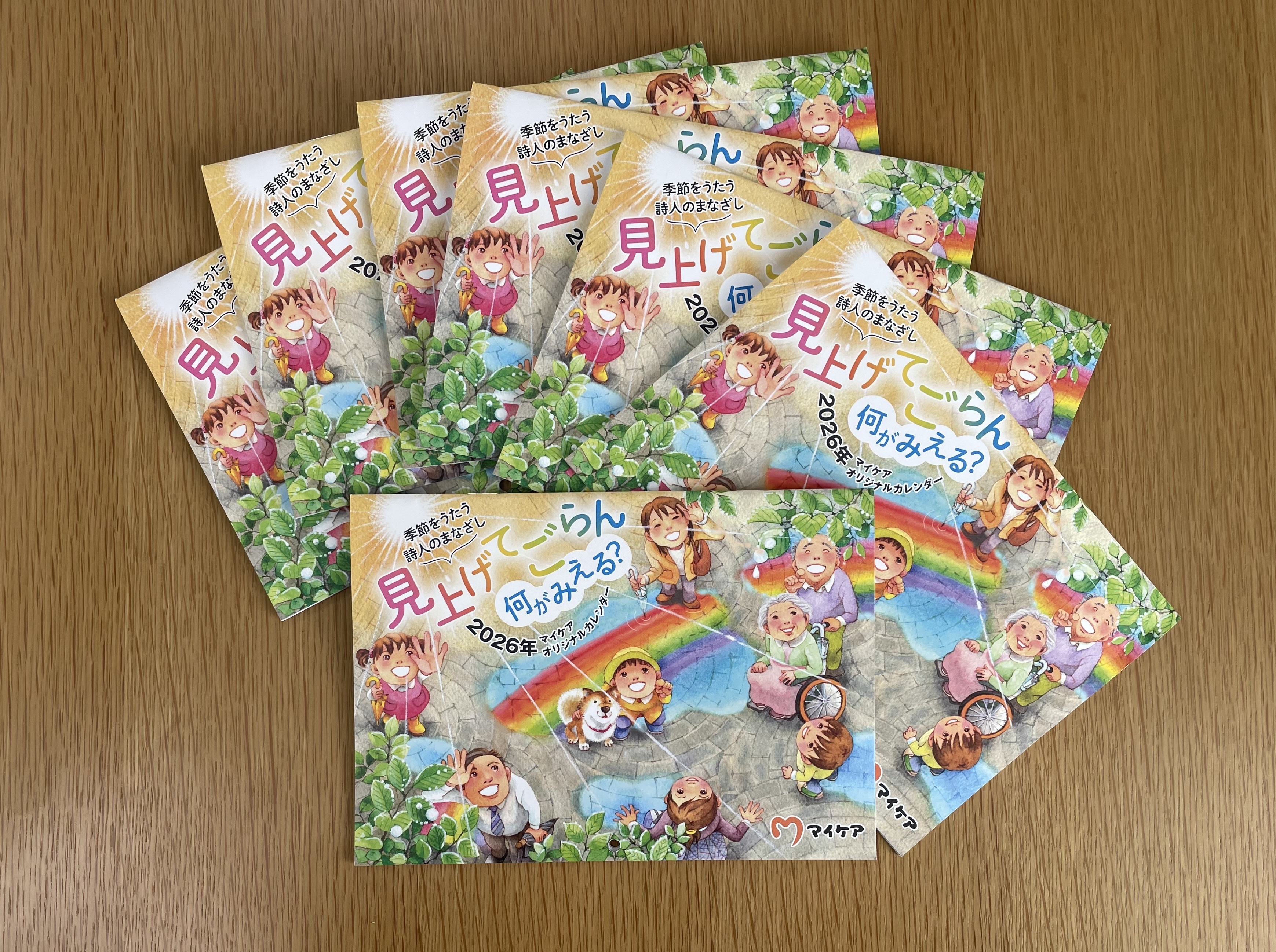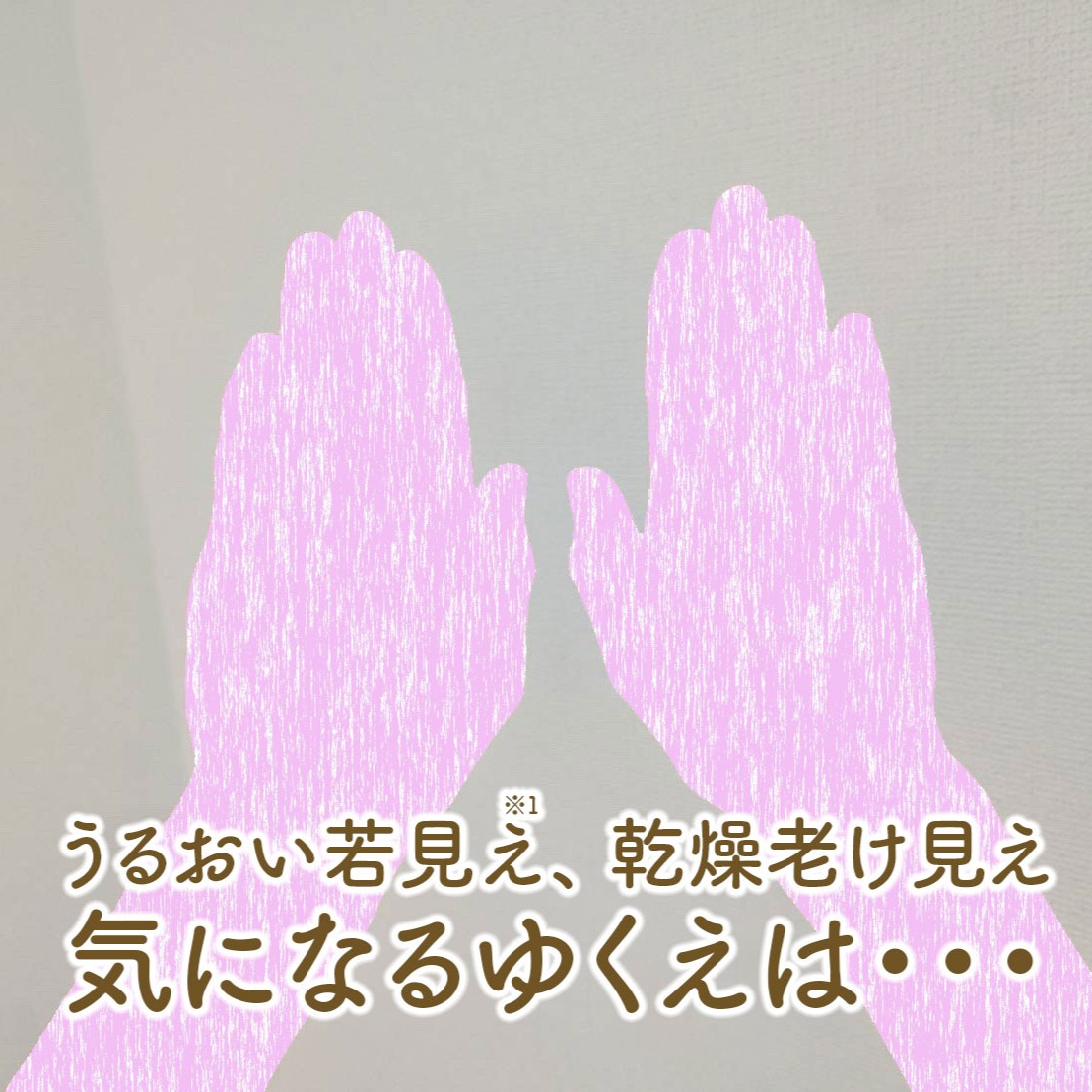2025.09.25
なぜ、日本人は紅葉を“狩る”のか?

やっと訪れた涼しさに誘われて、色づく野山の紅葉を見に行く。そんな秋の行楽にまつわる疑問を紐解きます。
“紅葉狩り”という言葉。疑問に思ったことありませんか?
手で摘むイチゴや、手でもぐブドウと違い、眺めるはずの紅葉を日本人は“狩る”と表現します。辞書で「狩り」という言葉を引くと「鳥獣を捕らえること」とありますが、「捕らえる」と「眺める」では大きく意味が異なりますよね。では、なぜ日本人は紅葉を“狩る”ようになったのか?時は平安まで遡ります‥‥。
平安貴族を虜にした紅葉の美しさ
紅葉を行楽として楽しむ文化は、『古今和歌集』や『源氏物語』にも記述が残っているとおり、平安時代から盛んになりました。秋の深まりと共に木々が一斉に染まる美しさに、当時の貴族も夢中になったそうです。平安貴族は牛車に乗って外出をするのが当然で、牛車から降りるのは品が無いこととされていました。
けれども、秋の山を彩る紅葉だけは、牛車から降りて自身の足で歩かないと見ることができません。そこで、当時の貴族は、面目を保ちながらも紅葉を楽しむために「これはあくまで、鷹狩りや鹿狩りと同じ“狩猟”として嗜んでいるのだ」と装ったのです。これが紅葉狩りの由来とされています。

平安貴族の乗り物である「牛車(ぎっしゃ)」は、車輪の付いた屋形を牛にひかせたもの。
牛車から降りない貴族でさえ、自身の足で険しい山を歩き、観に行くほど日本の紅葉は魅力的であることがうかがえますね。実際に、平安前期に編纂された 『古今和歌集』には、刻々と移ろう紅葉の色付きや散りゆく様子を愛惜を込めて詠んだ和歌が数多く残っているほどです。
さらに、赤・黄・緑など無数の色が織りなす紅葉を見られるのは、実は世界で日本だけ。そんな世界一の紅葉は、平安以降も日本人を魅了し続け、どの時代でも紅葉にまつわる歌や絵が数多く作られてきました。1000年の歴史を辿ることで、今まで当たり前に感じていた秋の景色が、いかに特別なものか思い知らされますね。
昔も今も大事なことは同じ
歩いて紅葉を見に行くことは、日本ならではの雅を楽しむだけでなく、心身ともに健やかに過ごすうえでも大切です。
当時、牛車を降りてまで紅葉を見に行ったという平安貴族。その代表格であり、以前NHKの大河ドラマで放送されていた『光る君へ 』の藤原道長は、運動不足により大病に伏しました。あれほど栄華を極めた道長でさえ、運動不足には打ち勝つことができなかったのです。貴族の楽しみである紅葉狩りをすることもできず、晩年を過ごすのはさぞ悔しかったことでしょう。
昔も今も、歩くことは健やかに過ごすために欠かせない習慣です。せっかく日本に生まれ育ったのですから、1000年の時を超えてもなお美しい秋の景色を、自身の足で楽しみましょう。

赤が黄色に変化するという意味の「もみつ」という動詞から派生して、現在では「もみじ」と呼ばれている。
今年の秋は、ぜひ紅葉狩りへ
歩いて紅葉を見に行くことは、1000年前から変わらぬ秋の楽しみ方です。秋も深まりはじめ、紅葉シーズンは目前。日本中を真っ赤に染めあげる、美しい景色を見逃さぬよう、ぜひお近くの山へ紅葉狩りに行ってらっしゃいませ。
<2024年 秋・冬号 Vol.66 31-32ページ掲載>














 だんらんWEB TOPに戻る
だんらんWEB TOPに戻る