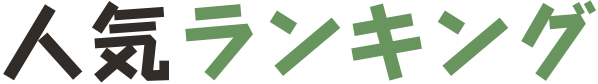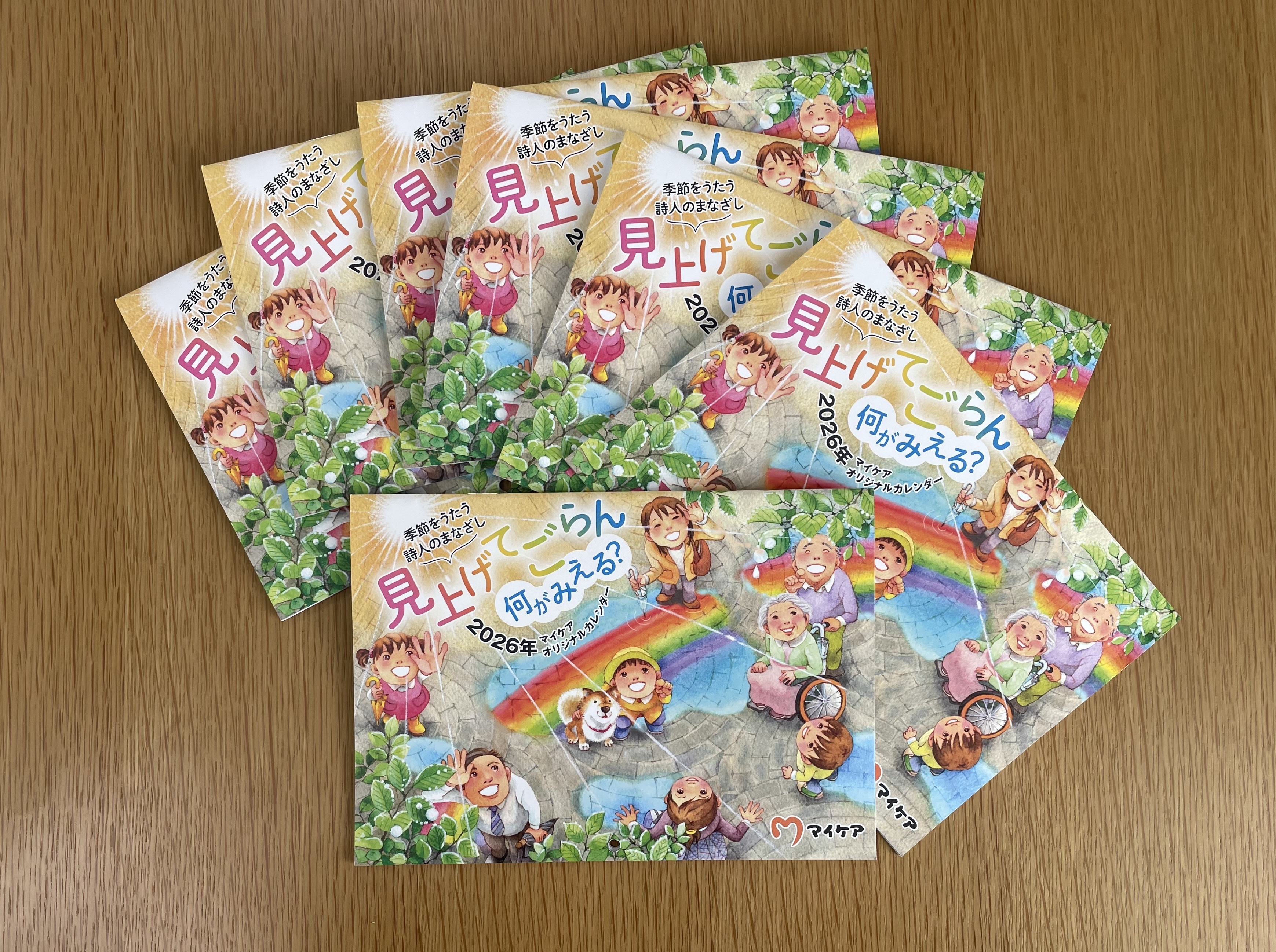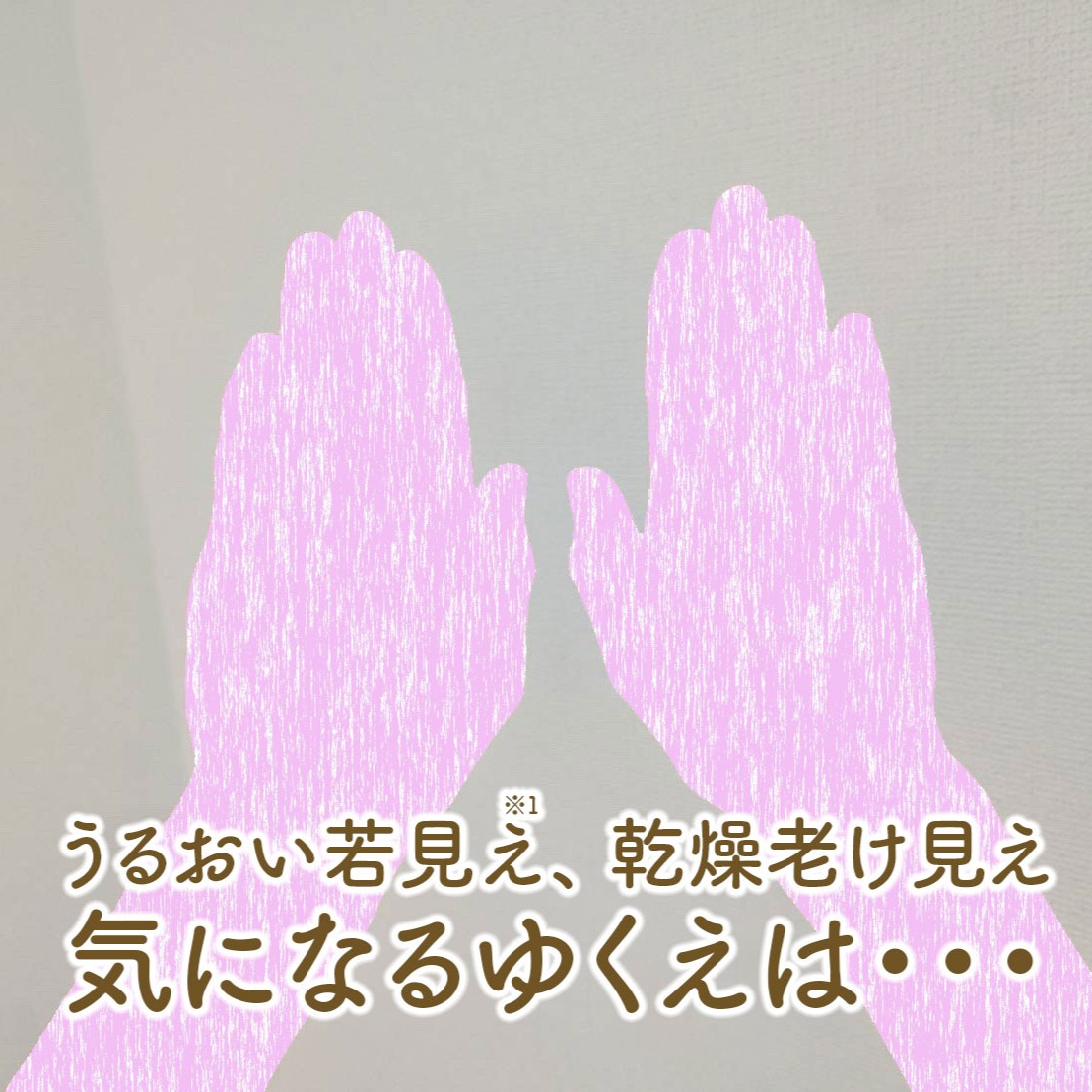2020.02.05
からだとこころを元気にするにっぽんのだし

世界に誇る和食の繊細で深い味わいをつくり出す、にっぽんのだし、その実力に注目してみました。
日本が誇る“旨み”文化
食べ物の味の基本となるものは、甘味、酸味、塩味、苦みの4つだと言われてきました。そこに、「ほかの要素もある」と新たに加えられたのが、旨みです。
日本から発信された「旨み」という味の概念は、国際的にも認められるようになり、今では「UMAMI」は世界の公式用語になっています。
旨みが凝縮された「だし」は、それだけで深い味わいがありますが、それが他の材料や調味料と組み合わさって、美味しさや味の奥行きをつくっていく、だから「だし」は大切なのです。
日本料理でだしをとる食材の多くは乾物です。海や山で収穫された材料は天日干しされ、乾燥する過程で雑味が抜けて旨みがいっそう高まっています。
こんなふうに、調理でだしをとる時間そのものは短くても、その元となる素材自体には、自然の力や人の手間ひまがたくさんかけられている、それが日本のだしなのです。
だしそのものに、それぞれの個性があり、他の食材との相性もあります。
どのだしを、どう活かし、どう組み合わせるか。その創意と工夫が、日本料理の繊細さ、奥深さにつながっています。

旨みの成分を組み合わせることで生まれる相乗効果。知っていれば、料理がひと味もふた味も変わります。
旨みの相乗効果
だしをとる場合、昆布とかつお節、というように、ほかのものと組み合わせることで、旨みが格段にアップすることが証明されています。
たとえば昆布の『グルタミン酸』とかつお節の『イノシン酸』を組み合わせると、旨み成分は約7.5倍に、昆布と干ししいたけのグアニル酸の場合は、なんと数10倍になるのだとか。これが、旨みの相乗効果なのです。
また、調理の過程で素材自体からも旨み成分が出ることで一層の味わいを生み出します。
そして、だしの中には旨みだけでなく、体にいいものがいっぱい溶け込んでいます。
昆布やかつお節に含まれているミネラルやカルシウムは、天日で乾かされることで、その量を増します。干ししいたけにもミネラルがいっぱい。
日に当たることで増えるビタミンDは、カルシウムの吸収を助けます。
味つけも、だしにコクがあれば、濃い味つけをしなくても充分に美味しさが感じられるので、薄めで大丈夫。
塩分控えめで、糖分などカロリーのとり過ぎも避けられます。薄味に慣れると、素材が本来もつ美味しさも実感できるはず。

お湯にかつお節を放つだけでもいいんですよ。かつお節は世界に数あるだしの中でも、最も早く手軽にとれる天然だしです。
だしをとる時間のぜいたく
叩けばコンコンと音がするほど固いかつお節を、ガシガシと削り器でかく。そんな光景も最近ではあまり見られなくなりました。
とはいえ、朝の台所は味噌汁のだしをとることから始まる……という家庭もまだまだあります。
だしの香りがキッチンにただよう時間は、ふるさとの食卓を想う時間。
お子さんのいるお母さんなら、夫や子どもたちの「美味しい」という顔を思い浮かべるのでしょう。だしをとるその向こうに、家族への思い、健康への気づかいも見えてきます。
今はサッサと振ってすませられる手軽な粉末のだしもあるけれど、だしの素材を水に浸し、湯を湧かし、といった一連の作業は、気持ちのゆとりという意味でも、ぜいたくな時間だという気がします。
かつお節を削ることから始めていた昔の日本の人は、そうしたひとときも大事にしていたのでしょう。
今夜は、家族の顔を思い浮かべながら、ゆっくりだしを引いてみてはいかがでしょう。家族の元気を願いながら、ひと手間かけて……。
<2011年 夏号 Vol.13 1-4ページ掲載>














 だんらんWEB TOPに戻る
だんらんWEB TOPに戻る