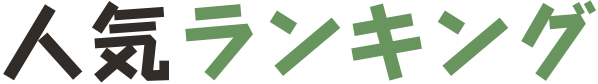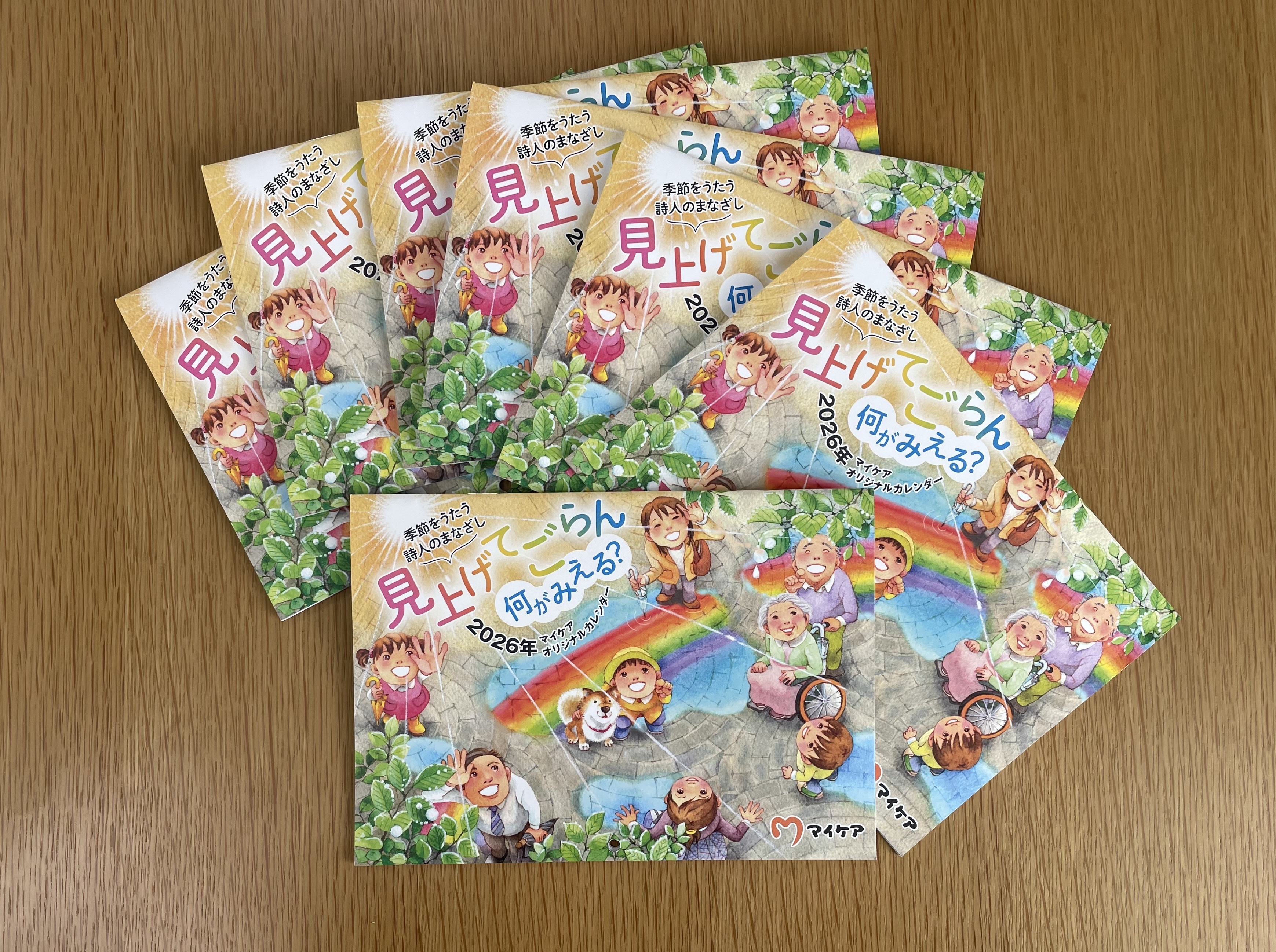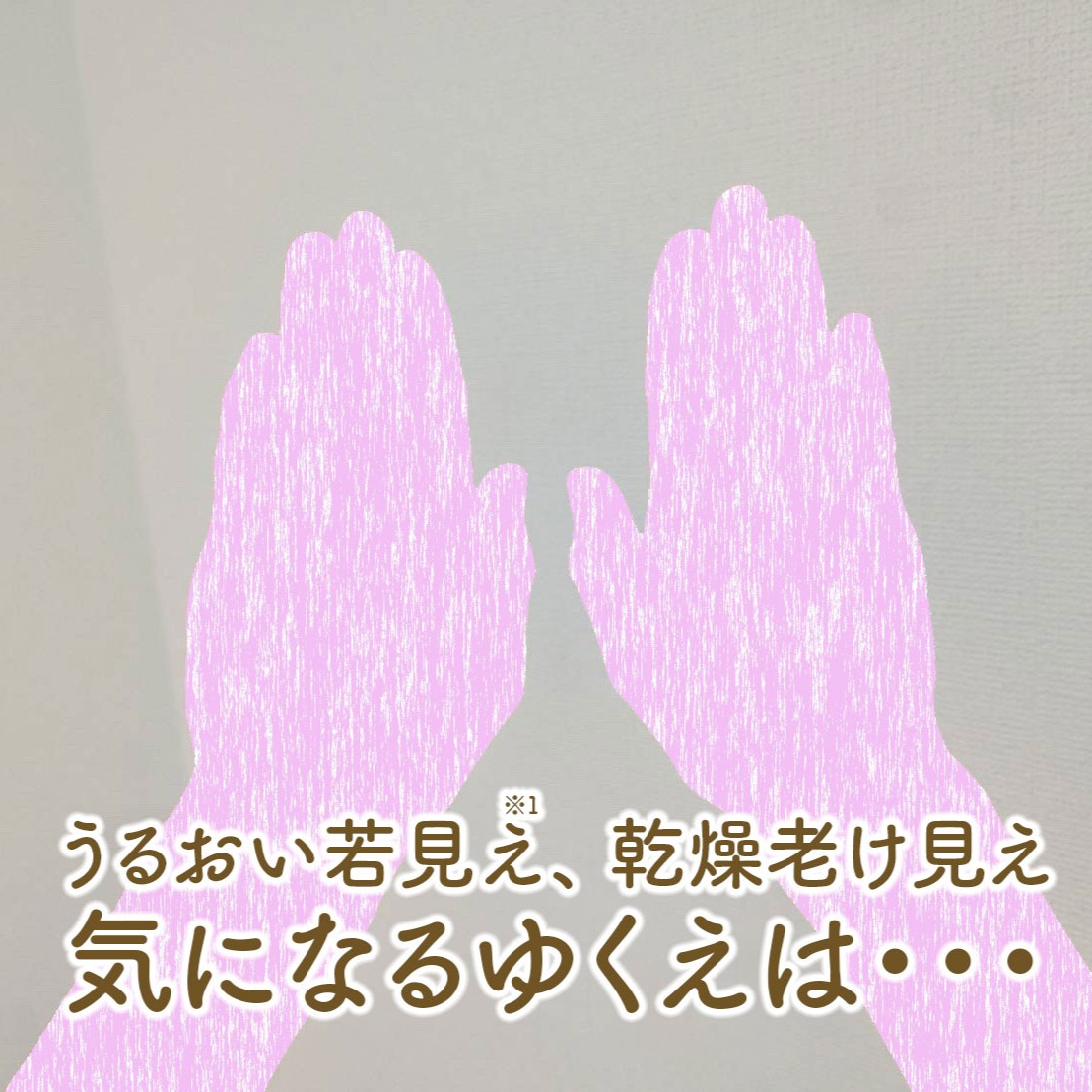2019.08.01
祭りで分かち合う喜び

祭りは風物詩であり、多くの人にとってのふるさとの風景ではないだろうか。東北の夏に活気づく、「ねぶた祭り」に向け、地元青森では多くの人が心を燃やしていた。
「伝統を理解してこそ新たな挑戦ができる」
ねぶた祭りの看板となるのが、大型の人形灯篭を乗せた巨大な山車。1年に渡り制作を担うのが「ねぶた師」だ。
北村春一(きたむらしゅんいち)さんは、お父様がねぶた師であったものの、仕事を継ぐ気はなかったそうだ。
「当時は反抗もあって東京で就職しました。でも、ねぶたを見ないと気が晴れなくて……」
生涯で唯一ねぶたを見なかった年、東北の観光案内のポスターを目にし、春一さんは思わず声を上げてしまったという。
「一目で『父のねぶただ!』と、わかったんです。父のねぶたは書割(絵の主線となる墨)の線が繊細で、鮮やか。父の仕事がわかったような気がしました」
当時お父様には弟子がいなかったため、この美しいねぶたがいつかは見られなくなってしまう。それは春一さんにとって心の転機になったそうだ。
しかし、実際にねぶたの制作に携わるようになってからは苦労が続く。
「2m以上の台座に乗せて動かすわけですから、遠くから見るだけでも印象は全く変わるんです。伝統だから大切にするわけではありませんが、型には必ず理由がある。それを理解してこそ新たな挑戦ができるんです」
複数のねぶたを手掛ける今も毎回反省ばかり。だから作り続けるのだと語ってくれた。

ねぶた師の北村春一さん(写真左)と扇子持ちの小山田拓治さん(写真右)。ねぶた祭りの話しをするお二人の目には、輝きとたぎる炎が見えるようだ。
“血がじゃわめぐ”ねぶた囃子
ねぶた師の想いに応え、山車を操り、魅せるのが「扇子持ち」である小山田拓治(おやまだたくじ)さんの役目だ。
「運行は、扇子持ちと、山車の四角につく5人組で行います。ねぶたが持つストーリーや背景まで想像できるように、ねぶた師とも話し、どう動かすかを決める。扇子持ちの仕事は練習なしの一発勝負。一切気が抜けません」
何しろ山車の大きさは、幅約9m、奥行き7m、高さ5m、重さは4tにも及ぶ。
当日最大4時間に及ぶ運行中、小山田さんは山車を曳く20人もの曳き手の顔だけを見つめ、後ろ向きに歩み続ける。
しかし、ねぶたを躍らせ客席に見栄を切った際、眼差しや歓声を背で受ける瞬間はこたえられないものがあるそうだ。
そして、このねぶたの運行に欠かせない祭り囃子を奏でるのが「囃子方」。20基以上のねぶたが出陣する青森市では、初夏、海沿いの岸壁で各団体の練習が行われる。
「ねぶた囃子が街中で聞こえてくると、津軽言葉で〝血がじゃわめぐ〟っていうんです。体がざわざわして、いてもたってもいられない」
そう語るのは囃子方である若井実(わかいみのる)さん。太鼓のリズムは単に力任せではなく、抑揚や調和を考え、踊り手が跳ねやすいように奏でることが重要なのだ。

2017年に北村さんが手掛けた『妖術師滝夜叉姫』。優れたねぶた作品に送られる「最優秀制作者賞」を受賞した。
津軽ねぶたは暮らしの花よ
囃子に合わせ、街全体を活気づけるのが、一基のねぶたに2千人近くも加わるという踊り手、「跳人」たちだ。
「らっせーらー!!」の掛け声と共に大きく跳躍するのは跳人の辻村大(つじむらだい)さん。
「生まれてすぐは親に抱かれて、大きくなったら友だちと。でも誰かと行かなくたって、行けば必ず誰かがいる。知らない人とだって一緒に跳ねたら仲間になる。それがねぶたなんです」
何がここまで彼らを団結させるのか。聞けば、大きくは冬の苦難があるという。
抑圧される冬を超え、短い夏を楽しもうとする思いが、心を一つにする。しかし、辻村さんはこうも言う。
「雪があるから水があって、産業もある。大変なこともあるけれど『ねぶたあるから頑張るべし』って。祭りは地域の潤いであり、互いへの励ましなんです」
青森に伝わる『ねぶた音頭』に「津軽ねぶたは暮らしの花よ」という一節がある。同じ地で暮らすからこそ、分かち合える喜びがあり、人が集まるからこそ、帰ってくる人がいる。
がまんの冬を超え、歓喜が花開く。青森に住む誰もが血を騒がせ、心を躍らせるねぶた祭りに向け、熱い季節は今、本番を迎えようとしていた。
<2018年 夏号 Vol.41 3-6ページ掲載>














 だんらんWEB TOPに戻る
だんらんWEB TOPに戻る