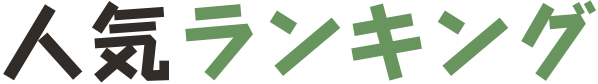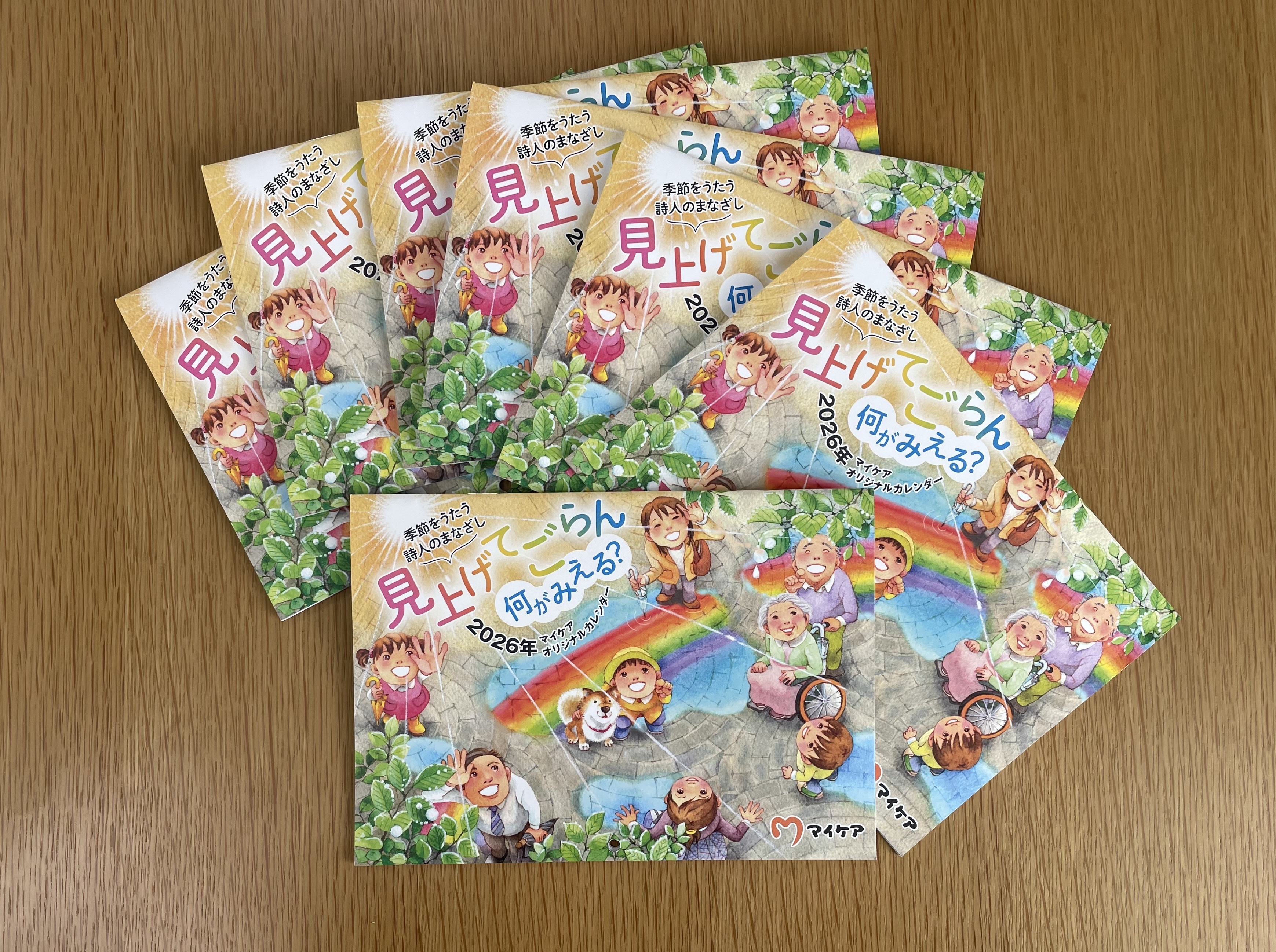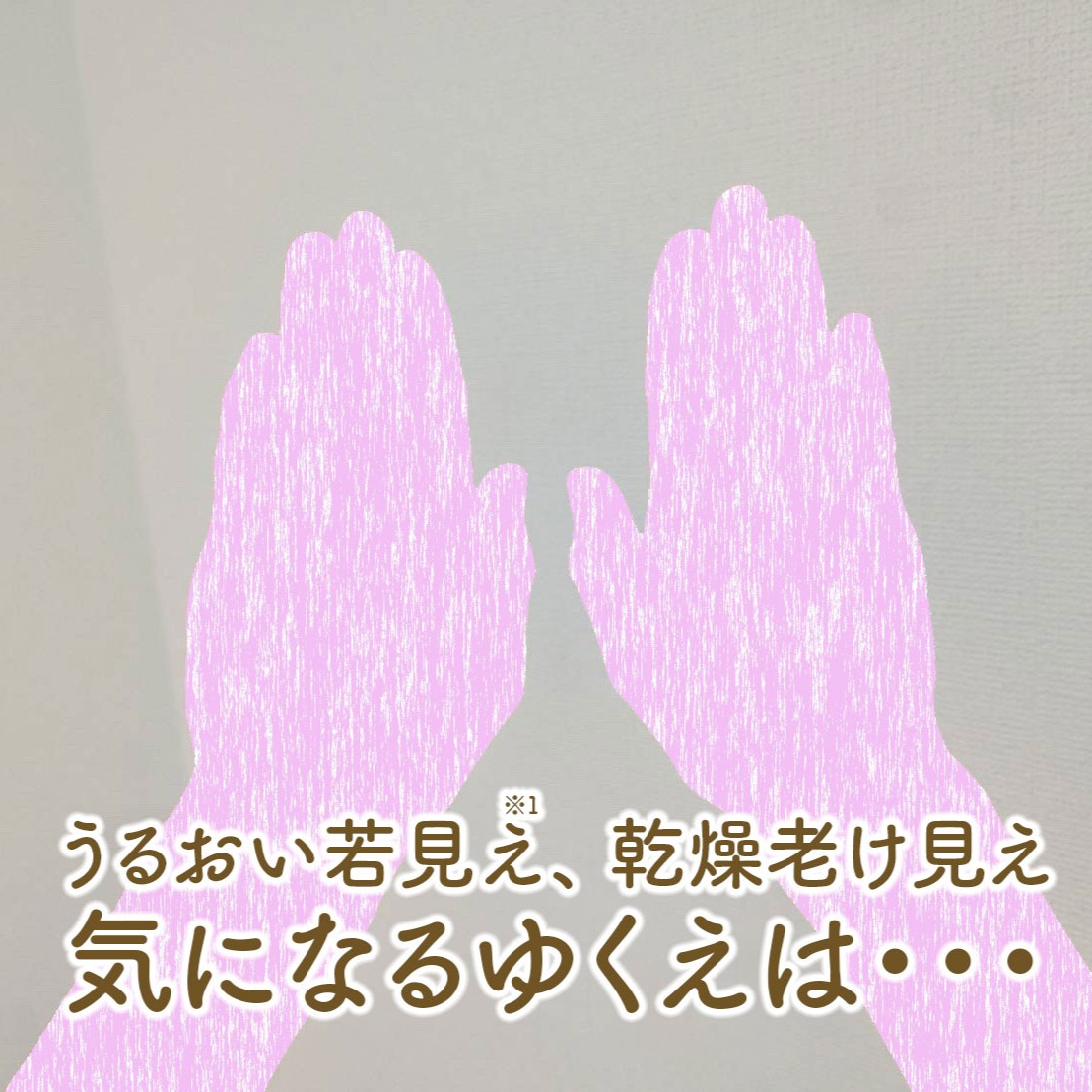2019.07.22
「涼」のある暮らし

クーラーも扇風機もない時代から、暑さと上手につきあう暮らしの知恵や工夫がありました。「涼」を演出する夏の過ごし方をあらためて見つめてみましょう。
夏を味わい、楽しむ昔ながらの暮らし方
四季のある日本では、移り変わる季節と向き合いながら、知恵を働かせ、工夫を凝らし、その季節ならではの上手な暮らし方を見つけてきました。
寒いなら寒いなりに、暑いなら暑いなりに。訪れるそれぞれの季節とうまくつき合い、味わい、楽しむ。それは、自然とともにある生活の中で育まれてきた、日本の文化です。
たとえば、日本家屋の軒の深いひさしは、夏の強い日射しをさえぎり、陰をつくります。
開閉が簡単で、取り外しもできる障子やふすまは、広く開け放つことで、外からの空気を家中に行き渡らせます。欄間や格子戸も、風の通り道をつくっています。
畳は、吸湿性にすぐれ、放湿作用もあり、汗ばむ夏に心地よさをもたらします。竹やよしの茎で編んだすだれなど、夏の暮らしの中にあるものは、風を招き、光を穏やかに取り込みます。
夏という季節にさからわず、受け止めて、自然の力を借りながら、暑さをやわらげる工夫が、形や素材に表れています。
さらに、軒下に風鈴を吊るしたり、打ち水をしたり、さまざまに涼しさを生み出しながら、夏の風情・情緒を楽しんだのです。

うだるような暑さの中、一陣の風がうれしい……。昔の人は、ふだんの暮らしの中に涼を見つけるのがとても上手でした。
涼を見つける、感じる
涼といえば、やはり、風。戸を開け放って部屋に取り込む自然の風を、昔の暮らしではとても大事にしたのです。
自然の風がなければ、うちわの登場です。手軽にやわらかな風をつくり出すうちわは、おもてなしにも使われ、各家庭には、江戸の頃庶民の間ではお客さま用のうちわも用意されていたとか。
風を室内に取り込む、日射しをさえぎるなど、物理的に暑さを抑えるだけでなく、目や耳など、五感で涼をとらえるのが日本人の感性です。
軒下に吊す風鈴は、透明感のある音色で涼を感じさせます。風にそよぐ樹々の葉、揺れる木漏れ日、川のせせらぎ、水の音、朝顔……。
感覚のアンテナを研ぎ澄ませば、さまざまなところに涼はあります。床の間の掛け軸を渓流や水鳥に掛け変えたりするのは、涼をいつも身近に感じるためです。
着るものにも、涼を見ることができます。日本の着物は季節にあわせた約束事がいろいろありますが、夏に着るのは、絽や紗、羅、麻など、薄物と呼ばれる、薄く透ける素材のもの。
着心地だけでなく、見る者に与える涼感に重きを置いているのです。

涼を取り入れた暮らしの工夫や演出で、夏の風情をたっぷり味わいたいものです。
涼をつくる、演出する
昔ながらの暮らしには、涼を生み出すための工夫や演出がいっぱいです。
ふすまをすだれにする。床の間の掛け軸も、涼を呼ぶものに。座布団は清涼感のある麻や、伝統的な藍染めに。藍には防虫殺菌効果があり、その独特な寒色系の色合いが、目から涼を呼び込みます。
また、お菓子にも涼を盛り込むのは日本人ならでは。くずや寒天といった透明感のある和菓子はみずみずしく、食感もまた涼味満点です。
くずきり、ところてん、水ようかん……もっと庶民的なところでは、かき氷。食べる冷え冷えのひと口に夏を感じるのです。
さて、夏のある日、ザルに盛った紫紺のナス、緑色のオクラの絵を添えた暑中見舞いのハガキをいただき、思わず暑さを忘れた瞬間がありました。返信は、朝露をつけたテッセンの花の写真。
暑中、残暑見舞いの便りは、夏の暑さをねぎらう日本の風習。季節をこうして意識し、親しい人に涼を届けることも、夏の楽しみにつながります。
* * *
春や秋にくらべて過ごしにくい夏も、上手に暮らしてきた日本人。夏のよさを味わう「涼」を、現代の暮らしにそわせながら、取り入れたいものです。
<2012年 夏号 Vol.17 2-6ページ掲載>














 だんらんWEB TOPに戻る
だんらんWEB TOPに戻る