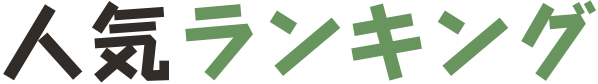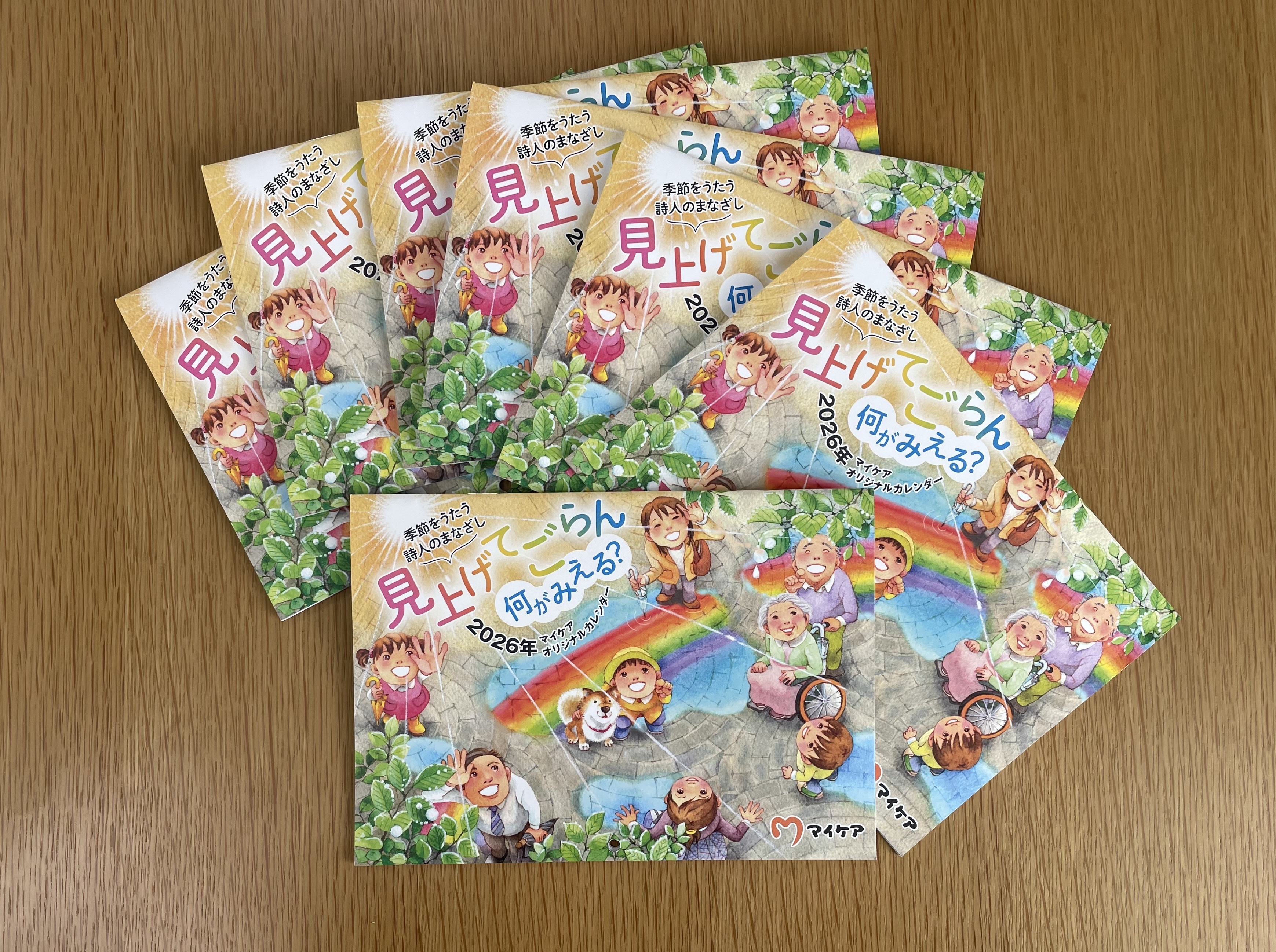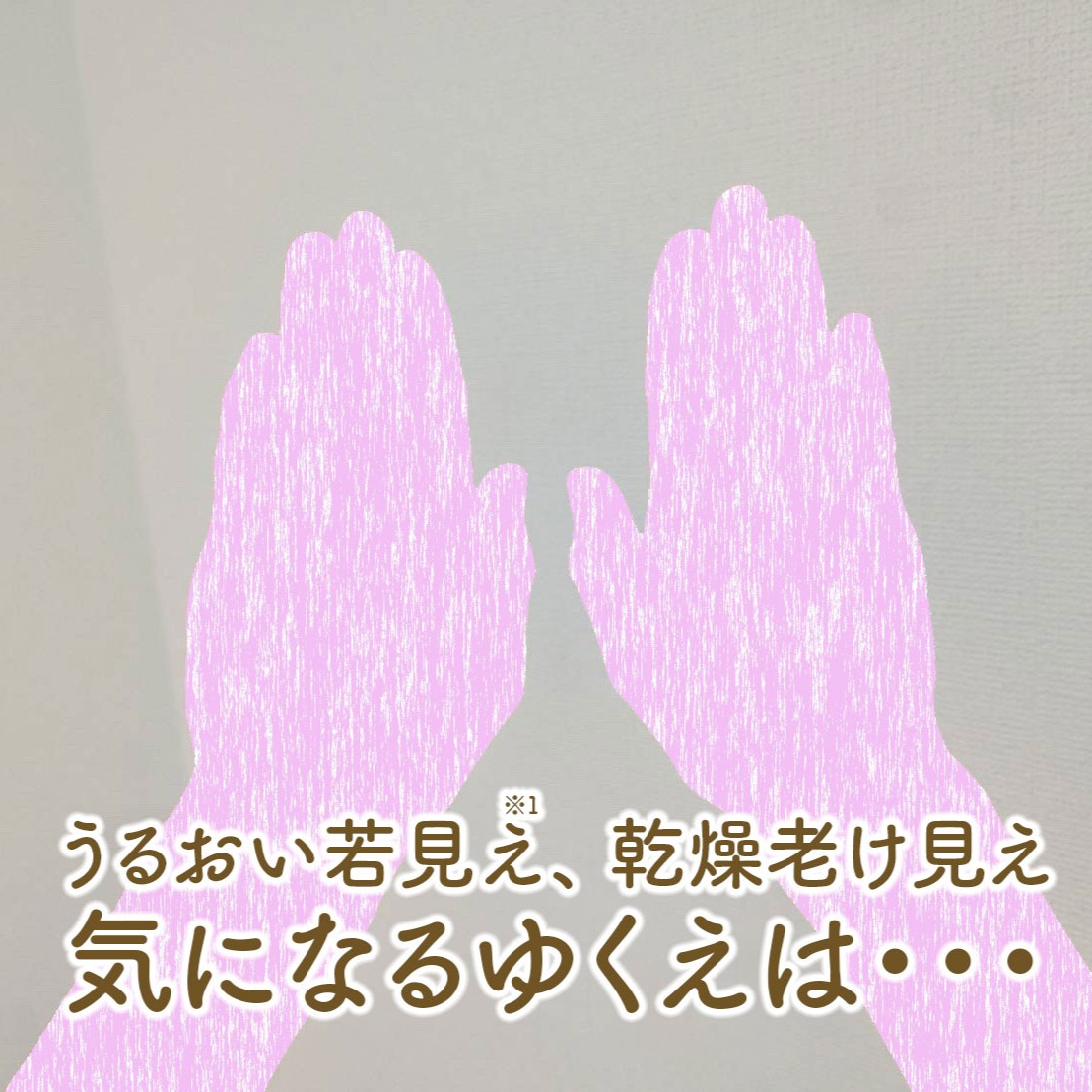2020.06.25
藍をもっと深く知る

まだ科学的なことが明らかになっていなかった時代から、愛されてきた藍色。藍のことをもっと深く探っていきましょう。
洪水流量は日本一、暴れん坊の「吉野川」が藍のふるさと
日本で一番の藍の産地といえば、阿波の国、徳島県の吉野川流域です。なぜこの地域で藍が発展したのでしょう。その理由はまさに、川にあります。
高知から流れる吉野川は、かつて毎年夏の終わりから9月にかけて発生する台風によって氾濫し、洪水の被害をもたらしました。
その水量は日本一で、洪水になると手がつけられない暴れ川として「四国三郎」と異名がついているほど。この環境では、秋に収穫時期を迎える稲作はできません。
その点、藍は3月に種を蒔いて、収穫は7月。しかも、洪水によって肥沃な土が流域に流れ込み、藍を育てるのに適した土壌を作ります。
本来多大な被害を及ぼす洪水を逆手にとり、地の利として活かしてきたのです。
また、布を丈夫にし防虫効果のある藍染めは、江戸時代に生活必需品となっていました。
そこで当時の徳島藩は藍の生産を奨励し、藍染めに欠かせない製法を知る人物を播磨(現在の兵庫県南西部)から呼び寄せ、品質の良い藍染めを大量に生産できるように後押ししました。
こうして徳島県は、江戸時代から今に繋がる藍の一大産地となったのです。

絞り染めした布地。陽にかざすと、さらに美しい濃淡が現れます。技法や布の種類によって、色も風合いも異なる表情の豊かさが藍染めの魅力。
一色に留まらない多彩な藍の色
藍で染めた独特の青は、「ジャパンブルー」と呼ばれ、日本の伝統を表す色として世界でも広く知られています。
藍染めの色は、手法や布の種類によって様々に変化し、微妙な濃淡のそれぞれに名前がついています。
例えば、ごく薄い水色=「甕のぞき」は、甕の中の水を覗いたときの色。本来、透明な水がうっすらと見えるほのかな青を表します。
また、限りなく黒に近く、かろうじて紺に留まっている=「留紺」。紺よりも濃く、光線の具合で赤みを帯びて見える深い藍=「褐色」は、鎌倉時代の武将たちに、縁起のよい「勝ち色」として好まれました。
色の多様さは、「藍四十八色」と表現され、日本人はその微妙な色合いの違いを楽しんできたのです。
青に染める草木染めの染料は藍だけのため、重ね染めにも欠かせません。藍だけで染めた色も多彩で魅力がありますが、他の染料と重ねることで様々な色彩を生み出します。
緑の葉を染料に使っても、藍がなければ緑に染めることはできないのです。同じように、紫なども藍があるからこそ生まれる色。
藍の青を重ねることで、日本の豊かな染料における色彩が生まれました。
日本の藍染めのルーツを辿ると、大陸に行きつきます。伝来の時期ははっきりしませんが、1800年前ごろ、弥生時代の中期には行われていたと考えられています。日本で藍染めに用いられている蓼藍は、その技法とともに伝わりました。
歴史を証明する現存品は正倉院宝物にあります。藍染めは、遥か昔から日本人の生活に溶け込んでいたようです。

左は型染めの型紙、右は板締め染めの板。どの技法も手仕事です。
豊かな色彩と効能、自然の力を宿す藍
藍染めは染料が水に溶けず、液体のなかで小さな粉の状態になっています。それが糸や布地の間に入って色が付着。色で繊維をコーティングすることで丈夫になり、擦れなどに強くなるのです。
藍には虫除け効果のある成分が含まれるため、農作業などの際に着用されてきました。
さらに燃えにくく、保温性にもすぐれていることから、火消しの半纏や蚊帳、産着、手ぬぐいなど、日用品にも多く用いられていたのです。
美しいだけではなく様々な効用を持つ藍染めは、昔から日本人に愛されてきた優れた高性能染料といえるでしょう。
藍染めは各地に伝わる様々な染色や織りの技法によって着物や小物に仕立てられ、人々の生活を支えてきました。
● 板締め染め
折りたたんだ布を色々な形の板で挟むことで防染し、様々な模様を染める染色法。
● 絞り染め
絞りは、織った布地を糸でつまんだり、縫い締めたりして防染した後に染める方法。つまんだ部分=「しぼ」が立体的に浮き上がり、独特の豪華さを醸し出します。
● 型染め
柄を切り抜いた型紙を使い、染めない部分に糊を置いて防染し、その後布地を染めていきます。絵画のような柄がつけられるのが特徴。小紋や型染め友禅など、また浴衣でもよく目にします。
化学染料が主体となった今も、古いハッピや浴衣、老舗ののれんなどに伝統的な藍染めを見つけることができます。
味わいのある昔ながらの青に懐かしさを感じるのは、私たち日本人が、美しい藍の色に今も変わらず恋しているからかもしれません。
機会があればぜひ、天然藍の藍染めに触れてほしいと思います。
<2019年 夏号 Vol.45 5-8ページ掲載>














 だんらんWEB TOPに戻る
だんらんWEB TOPに戻る