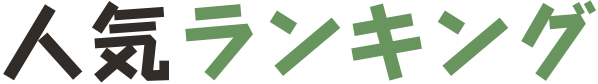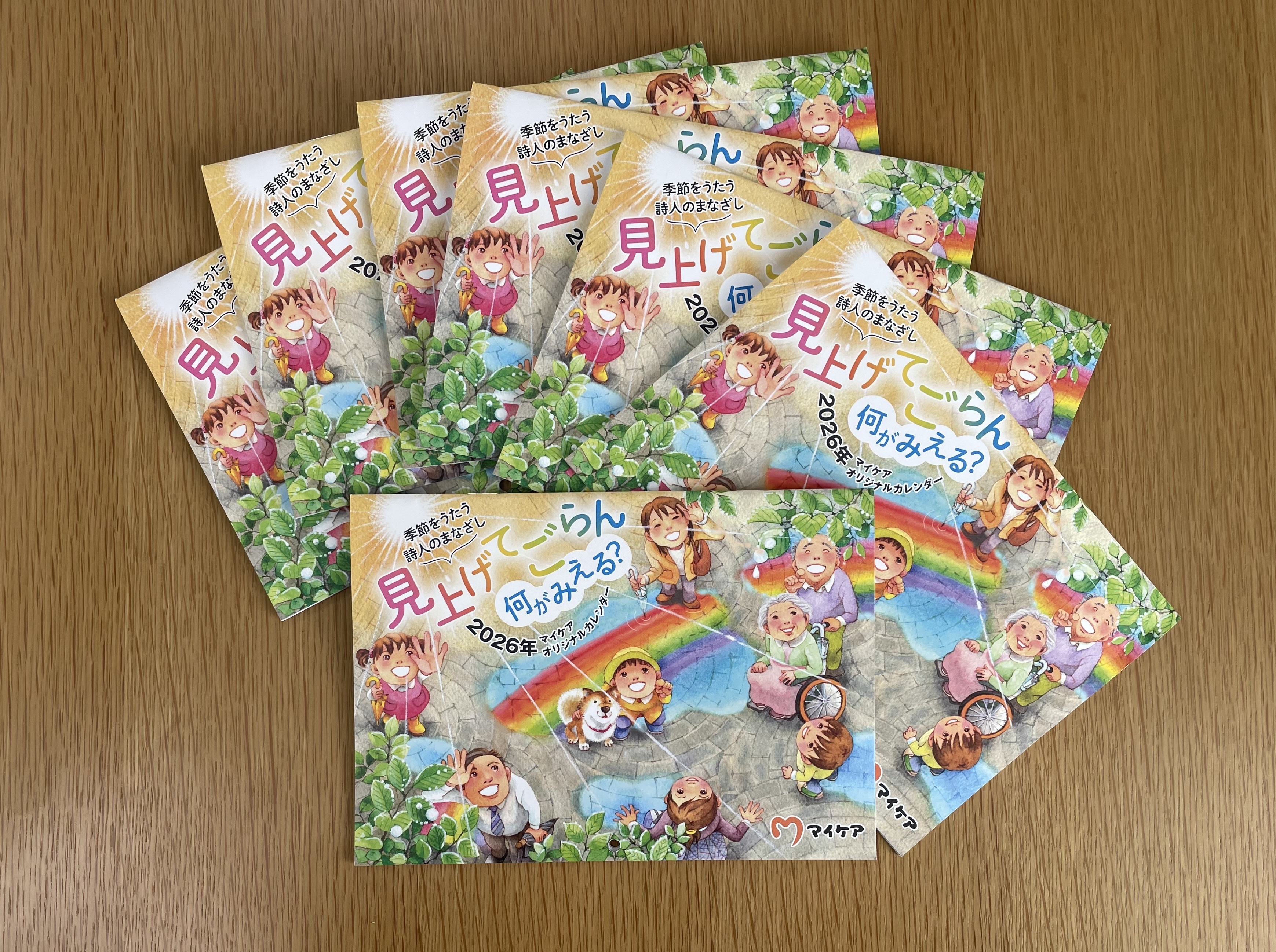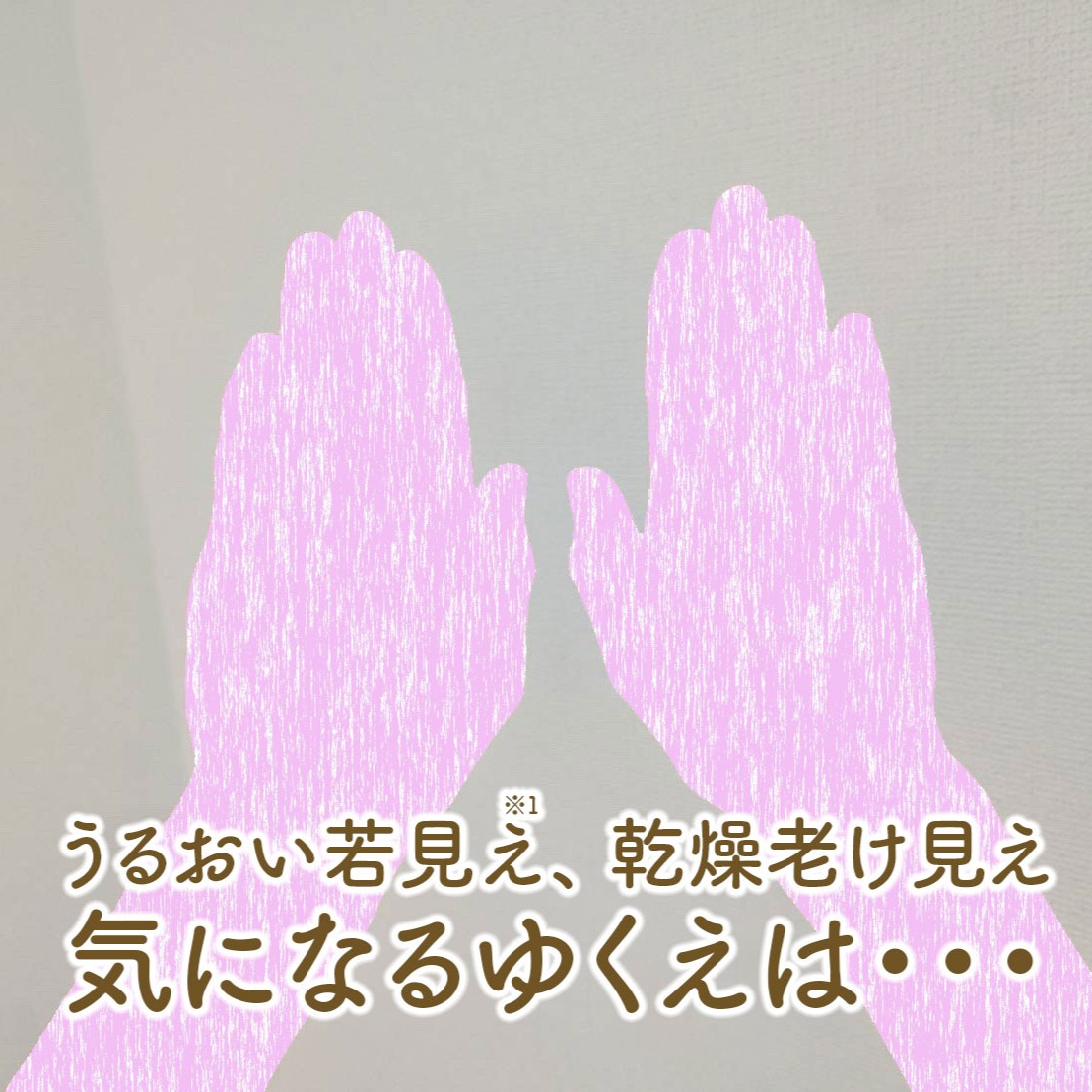2018.10.18
日本の色・四季の色

私たちのまわりにたくさんある「色」について調べてみると、日本人の色に対する思いが見えてきました。
季節のうつろいを色によせて
季節の変化を「色」で感じることがあります。秋であれば、樹々が色づく赤や黄色。
たとえば米農家の人は、植えた稲が青々と育ち、やがて実った稲穂が黄金色に輝き、それを刈り取って土の色が見える、その田んぼの色の変化で1年が過ぎるのを実感すると言います。
春夏秋冬のある日本で暮らす私たちは、四季折々の自然の変化を、その季節の色とともに強く印象づけられ記憶していることが多いようです。
また、河川や湖、平野と、変化に富んだ地形、豊かな自然がある日本では、さまざまな動植物が生息し、四季の移り変わりとともに、目に映るものは彩りを変えます。
そうした中で暮らすことが、日本人の色に対する感覚を鋭敏にしたのでしょう。
たとえば、桜色、撫子色、山吹色、また鶯色、鳶色など……。四季の草木や鳥など、日本の伝統色には、自然からとられたものが数多くあります。
今回は、紅葉の赤や実りの黄金色が山野を彩る“秋”に着目して、さまざまな色を訪ねてみたいと思います。

秋の山々の風景にも、「きれい!」と言うだけではもったいないほどの数多の色が隠れています。
山に見つける秋の色
秋になると、山肌は錦絵にも例えられる華やかな色に染まります。同じ赤でも、赤みが濃かったり、オレンジ色を帯びていたり、色合いが少しずつ違います。
たとえば、山の端は見事な紅色、その下は韓紅(からくれない)というように。紅色は冴えた濃い赤。韓紅はそれより少しやわらかみのある赤です。
黄色も、濃くつややかな黄色なら鬱金色。明るく冴えた黄色なら黄檗色といった色名で言うと、それぞれの色の持つ味わいがより伝わる気がします。
日本の色の言葉は、紅葉を表現するものだけでも何十種類とあるそうです。
また、秋は実りと収穫の時期。子どもの頃の秋の記憶は、こうべを垂れた稲穂が揺れる田や、たわわに実った柿の木……。祖父母の住む田舎に行ったときの里山の光景です。
柿は「柿色」ですが、この柿色も、熟した柿のような黄赤色は「照柿」、くすんだ黄赤色は「洗柿」、これより薄いと「洒落柿」という色の名がつけられているそうです。
日本人は、柿の状態によるわずかな色の違いさえも大事にしたのですね。

空、キノコ、アキアカネ、和菓子……日常にも秋の色彩は溢れてます。
日常の中の身近な秋の色
私が普段目にするものにこれまで知っていた以上の色があるのを知って、世の中が色彩にあふれていることに気がつきます。
公園に咲いているコスモス、高く澄んだ空の青、飛んでいた赤とんぼ……これまで気にもとめなかった道ばたの草花も、それぞれ自分の色をもっている。そんなふうに考えると、とても愛おしく感じました。
風景を楽しみ散歩しながら、よく行く和菓子屋さんを覗いてみました。栗を使ったもの、モミジをイメージしたもの……並ぶお菓子にも秋の風情です。
色も、柿色や黄色、茶色系と、あたたかみのある色合いのものが多くなっています。季節の色に敏感な和菓子の職人さんの表現力に、あらためて感じ入りました。
昔の人は、季節の変化やうつろいを言葉にとどめ、たくさんの美しい色の名前を生み出してきました。
聞くだけで、そのイメージが沸いてくるような色の名前を知り、明日から見る景色の中に、どんな色をみつけられるか、どれくらい色の違いを感じられるか、楽しみです。
<2014年 秋・冬号 Vol.26 17-22ページ掲載>














 だんらんWEB TOPに戻る
だんらんWEB TOPに戻る