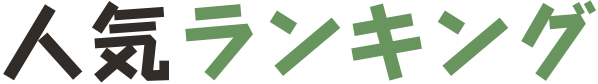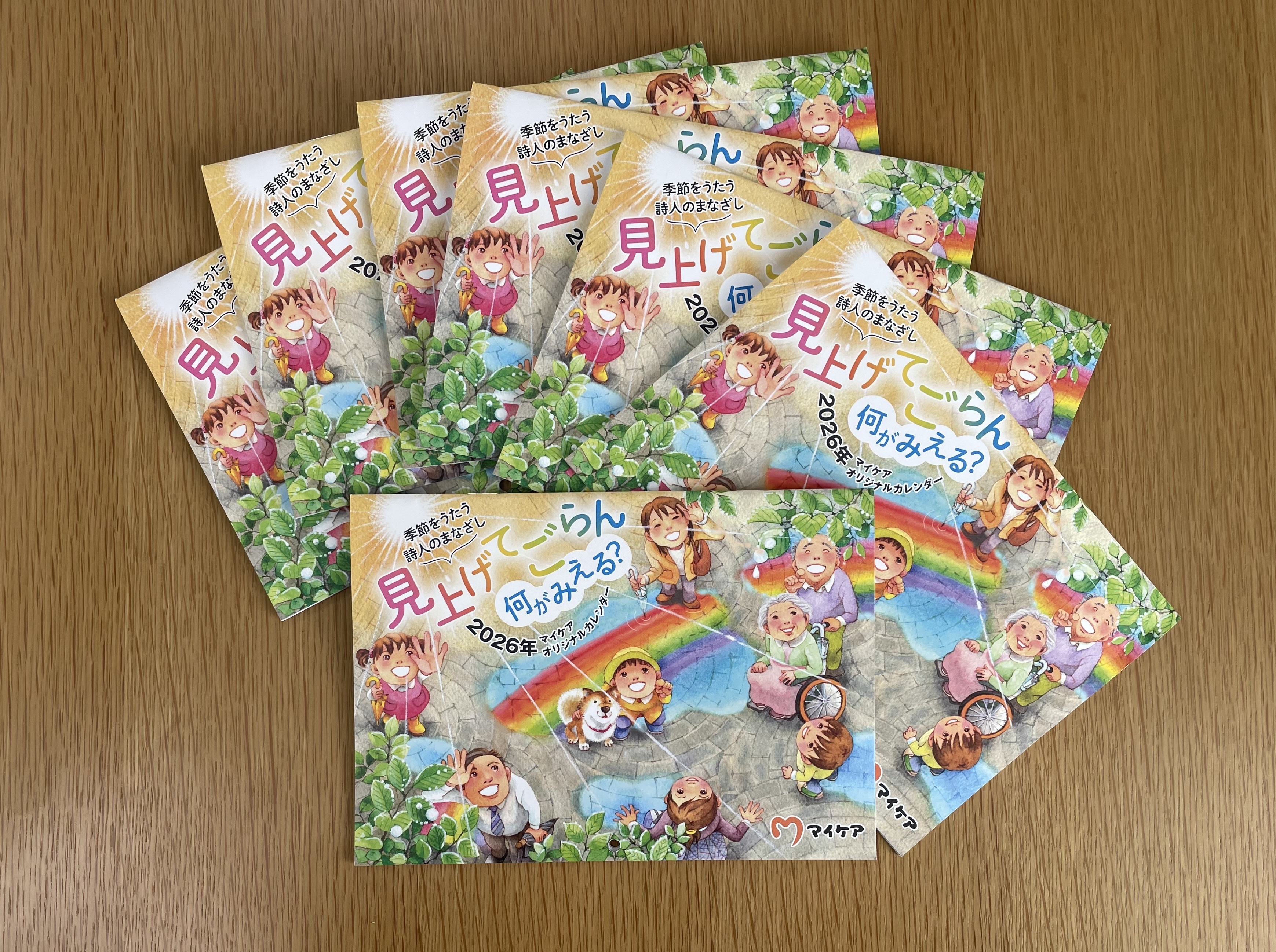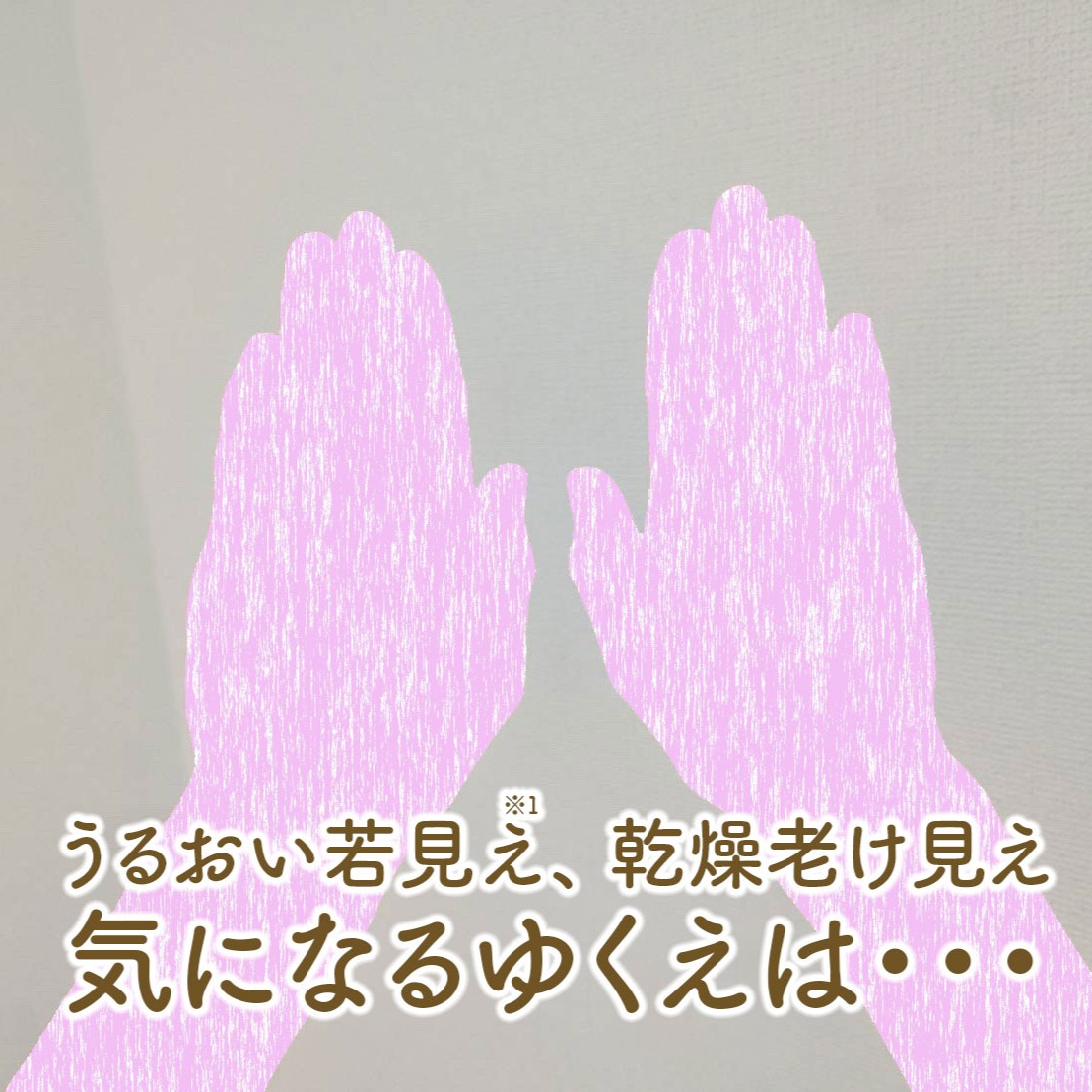2018.02.19
身も心もしあわせにつかる「にっぽんのお風呂」

湯船から出たあとも、いつまでも、ほっこり、あったかいものです。
湯船につかるしあわせ
いま何をいちばんやりたいですか?
「たまったお湯のお風呂に入りたい」
宇宙から無事地球に帰還した古川聡宇宙飛行士の発したひと言は、すべての日本人をうなずかせたのではないでしょうか。
湯船にからだを沈めれば、身も心もやわらかくほぐれていくよう。日本人にとって、お湯につかることそのものが、心地よいひとときです。
そんな日本のお風呂も、外国人から見れば不思議がいっぱいのよう。例えば「海外では浴槽はからだを洗うところ」という国が多い中、日本人が湯船にしっかりつかるのを見てびっくり。資料を探ると、その理由に「日本は気候が多湿で、汗をかくから」「湯を沸かす水や燃料が豊富だった」と挙げられています。
でも、それだけではないはず。そこで蒸し風呂から、湯船につかる方式に変わった江戸時代のことを振り返りながら推察してみます。
はじめは半身浴のように浅く張ってあったお湯が、だんだん深くなって……。人々はお湯の心地よさを体感していったのでは。夏はさっぱり。からだの芯から温まるので、日本の寒くて冷える冬にも、うってつけです。
こうした人々の実感から、湯船につかる入浴法が定着していったのかもしれません。

人と人とが心を通わせる時間「入浴」。日本人では当たり前でも、外国人から見れば…?
家族で温まるのもいい
親子が一緒に入浴するのは日本ではよくある光景。それも、外国人には信じられないのだそうです。浴室はきわめてプライベートな空間。家族であっても、そこには立ち入らないのです。
日本では、むしろ親子が一緒に入るのは家族円満、仲のよさのあかし。温泉地の宿には貸切の「家族風呂」もあるくらいです。
外国人は、日本人がハダカで大勢の他人と一緒に銭湯や浴場に入っているのにも驚きます。宗教的に、人前でハダカを見せることに抵抗感があるのです。
けれど、日本人にとっては仏教寺院の「施浴」という共同入浴がお風呂のルーツ。その後の銭湯文化もあり、他人と一緒にハダカで入浴することに抵抗はありません。むしろ、江戸時代の銭湯が庶民の社交場であったように、背中を流したり、流されたり、「ハダカのつきあい」は、本音で語らう親しさのあらわれ。温泉、銭湯、健康ランドなど、みんながハダカで入る入浴施設の豊富さは日本ならではと言えるでしょう。

今も昔も、「銭湯のあり方は変わっていないな」と感じる笑顔です。
入浴コミュニケーション
日本人にとってお風呂は、昔から心の交流の場。銭湯に来られたお客様にお話しを伺ってみると、入浴にはからだを清潔にする以外にも、もっともっといろんな効用があるようです。
会社員のある男性は、週末に小学生の息子と一緒にお風呂に入る時間をとても大事にしていると話してくれました。「お風呂だとね、息子も学校のこと、友だちのこと、いっぱい話してくれるんだ」と。親子の貴重なコミュニケーションタイムなのだそうです。
「いつも、おばあちゃんの背中を流してあげるの」と嬉しそうに話してくれた小学生の女の子もいました。温まって、気持よくて、お風呂の中では会話も弾みます。
家族だけに限りません。銭湯や旅先の大浴場なら、赤ちゃんからお年寄りまで、世代を超えた人たちが一緒にお湯につかって、見知らぬ人と自然に笑顔でお話できたりします。家族で入っても、仲間と入っても、知らない人とでも楽しいのが日本のお風呂なのです。
<2012年 新春号 Vol.15 1-5ページ掲載>














 だんらんWEB TOPに戻る
だんらんWEB TOPに戻る