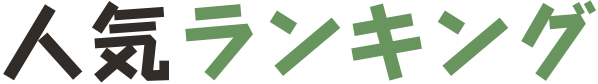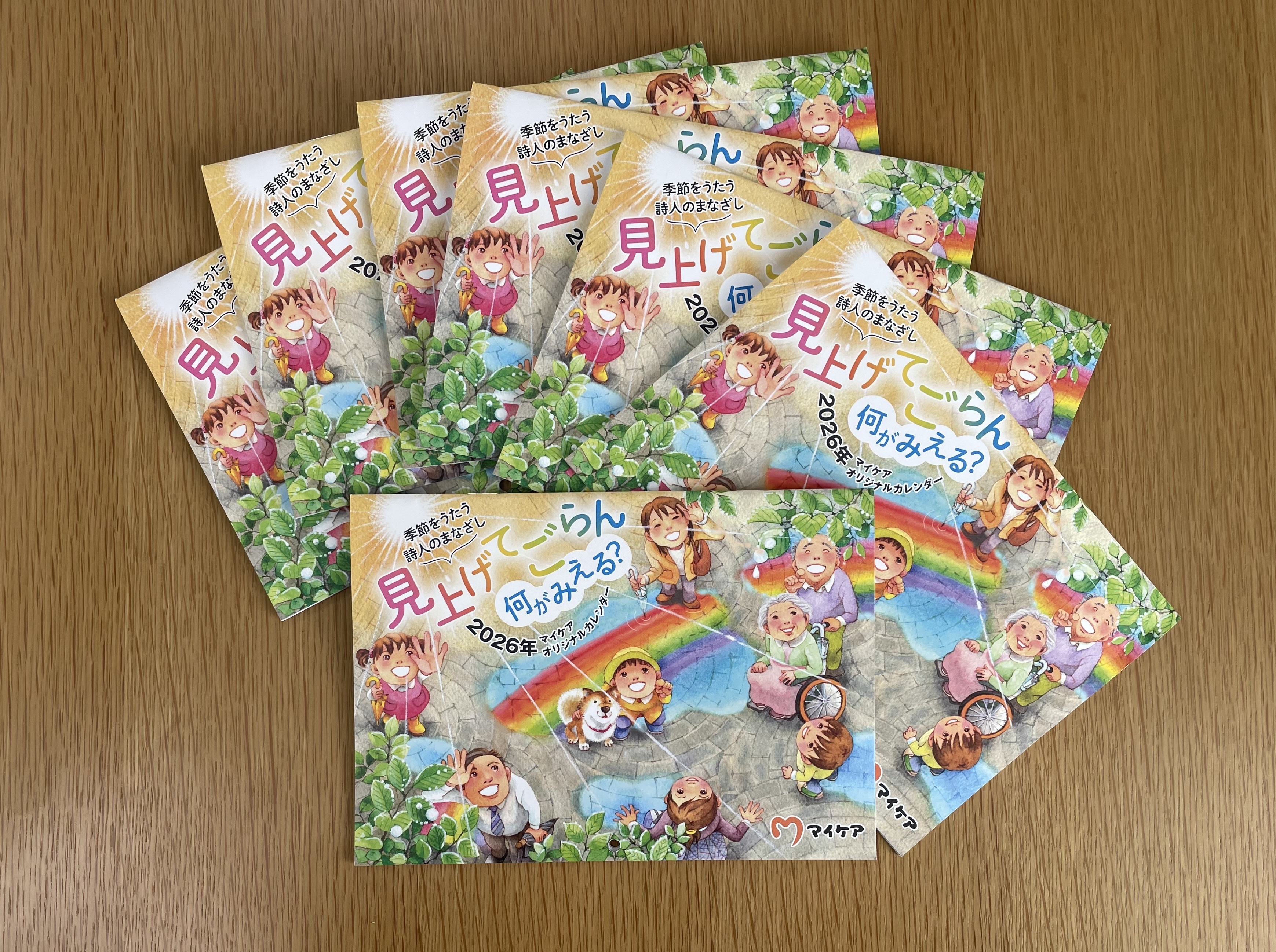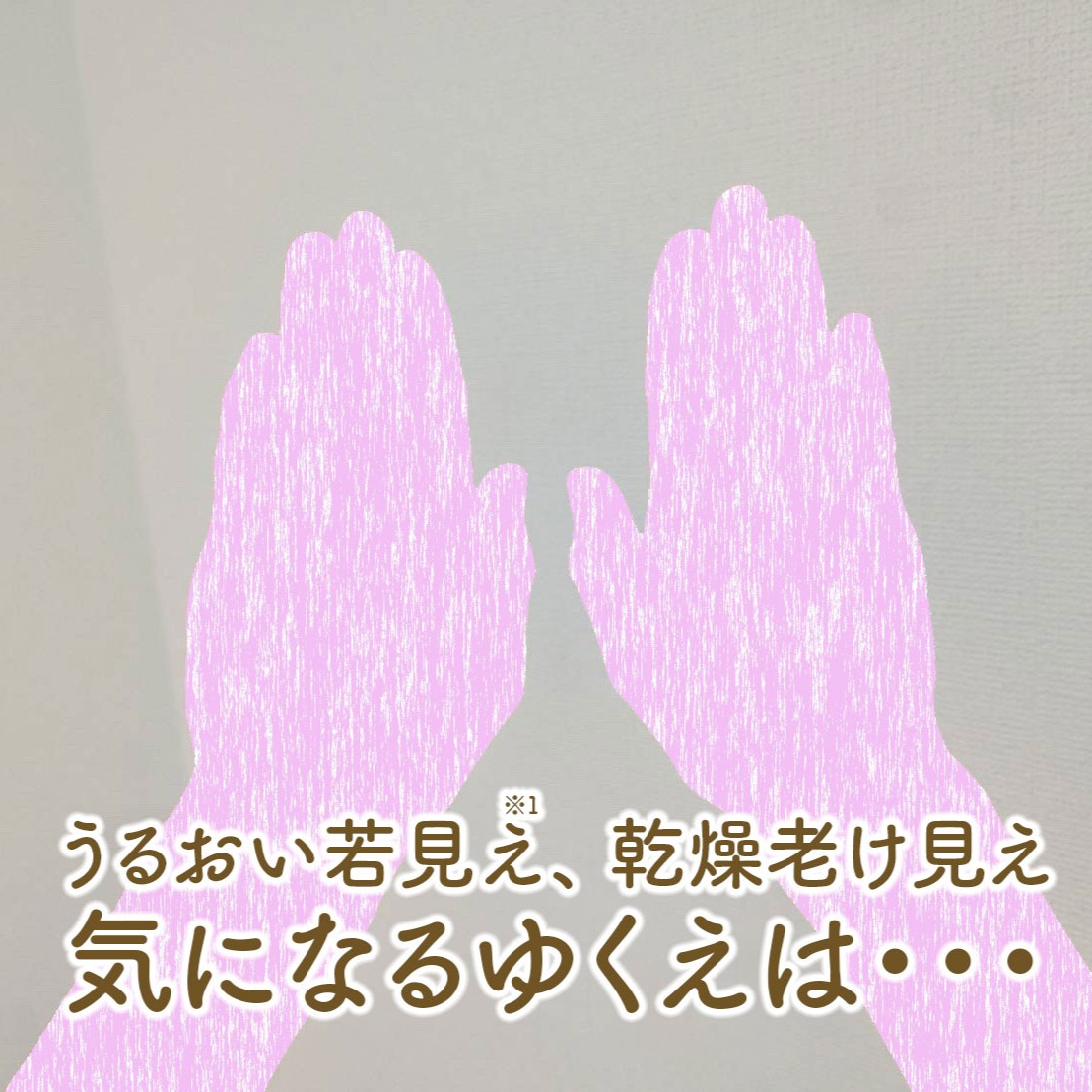2018.12.13
私たちとともにある日本の神様

日本人は、季節や行事、物や家の中にも神様はいる、という感覚を持っています。私たちとともにある「神様」の世界を見てみましょう。
日本には「八百万(やおよろず)」の神様がいるそうです
そもそも「八百万」とは、とても多い数を表す喩えです。
日本では太古の昔から山や岩、木、水などの自然に神様が宿っていると考えられてきました。
そして、自分が暮らす土地や住む家などにも神様の存在を感じてきました。「八百万の神」とは、そうした神様の総称といえます。
自然は多くの恵みをもたらしてくれる一方、時には嵐や地震などによる災害を招くこともあります。
人々は自然を人智の及ばないものとして捉え、神様の存在を感じてきたのではないでしょうか。
そして、日本人には海外のものを独自にアレンジする特性があります。
六世紀に仏教が入ってきた時も、「外国の神様」として受け入れました。新しい宗教も「八百万の神」の一つになるので、日本の神様は増える一方でした。

季節の移ろいや暮らしの中で、私たちはたくさんの神様に出会っているようです。
四季折々の神様
はっきりと四季を味わえるのも日本ならでは。春夏秋冬を通して、気付かない間にたくさんの神様と出会っています。
○冬・早春
<新年を運んでくる年神様>
年神様は元日に各家庭を訪れます。年神様をお迎えするために、年末に大掃除をして、神様が宿る門松を立て、鏡餅を供えます。
お正月は年神様をおもてなしして、新しい年を家族が無事に過ごせるよう祈る期間なのです。
○春
<春をもたらす女神>
奈良の佐保山に住む佐保姫は春の神とされ、機織りや染色が得意な神様で、春霞を作るという神話があります。
佐保山の麓には桜並木があり、一斉に咲いて春の訪れを知らせます。桜前線も佐保姫の手招きでやってくるのでしょう。
○夏
<大海原を支配する海の神様>
魚など海に住む生き物を統率し、潮の満ち干を操るなど、海を支配するのはワダツミという神様です。その大きな力で海に囲まれて暮らす私たちを守ってくれています。
○秋
<風の強弱を操る風の神様>
古代の人々は、神様の息が風を起こすと考え、風の神様シナツヒコを祀り、暴風を鎮めるようお祈りしました。
鎌倉時代にモンゴルが攻めてきた際、風の神様が暴風を起こして撃退してくれたと信じられ、伊勢神宮にはシナツヒコを祀る風日祈宮があります。

中には優れた人物や鬼を祀る神社もあります。神様は形にとらわれません。
「人」や「鬼」の神様
実在した歴史上の人物を神様として祀る神社も数多くあります。
菅原道真公を祀った天満宮もその一つです。
左遷で失意のうちに亡くなった道真公の魂を鎮めるために祀られたのですが、次第に学問の神様として信仰を集めるようになりました。
鬼を神様として祀る地域もあり、秋田県男鹿半島に伝わる新年のナマハゲの行事は「鬼は厄災を祓う来訪神」としています。
鬼は恐ろしい悪霊や病気を追い払ってくれる頼もしい神様でもあるのです。
鬼を神様として祀っている神社の節分では「福は内、鬼は内、悪魔外」「鬼は内、福は内」などといって、鬼を呼び込むそうです。
このように、目には見えず、声も聞こえないけれど、きっと私たちの周りにはたくさんの神様がいます。
楽しいことやうれしいことは一緒に喜んでくれ、悲しいことや苦しいことはそっと追いやってくれているのかもしれません。
そんな神様に囲まれて生活していると思うと、心強く、日々の暮らしが彩り豊かになっていく気がします。
<2018年 秋・冬号 Vol.42 23-28ページ掲載>














 だんらんWEB TOPに戻る
だんらんWEB TOPに戻る